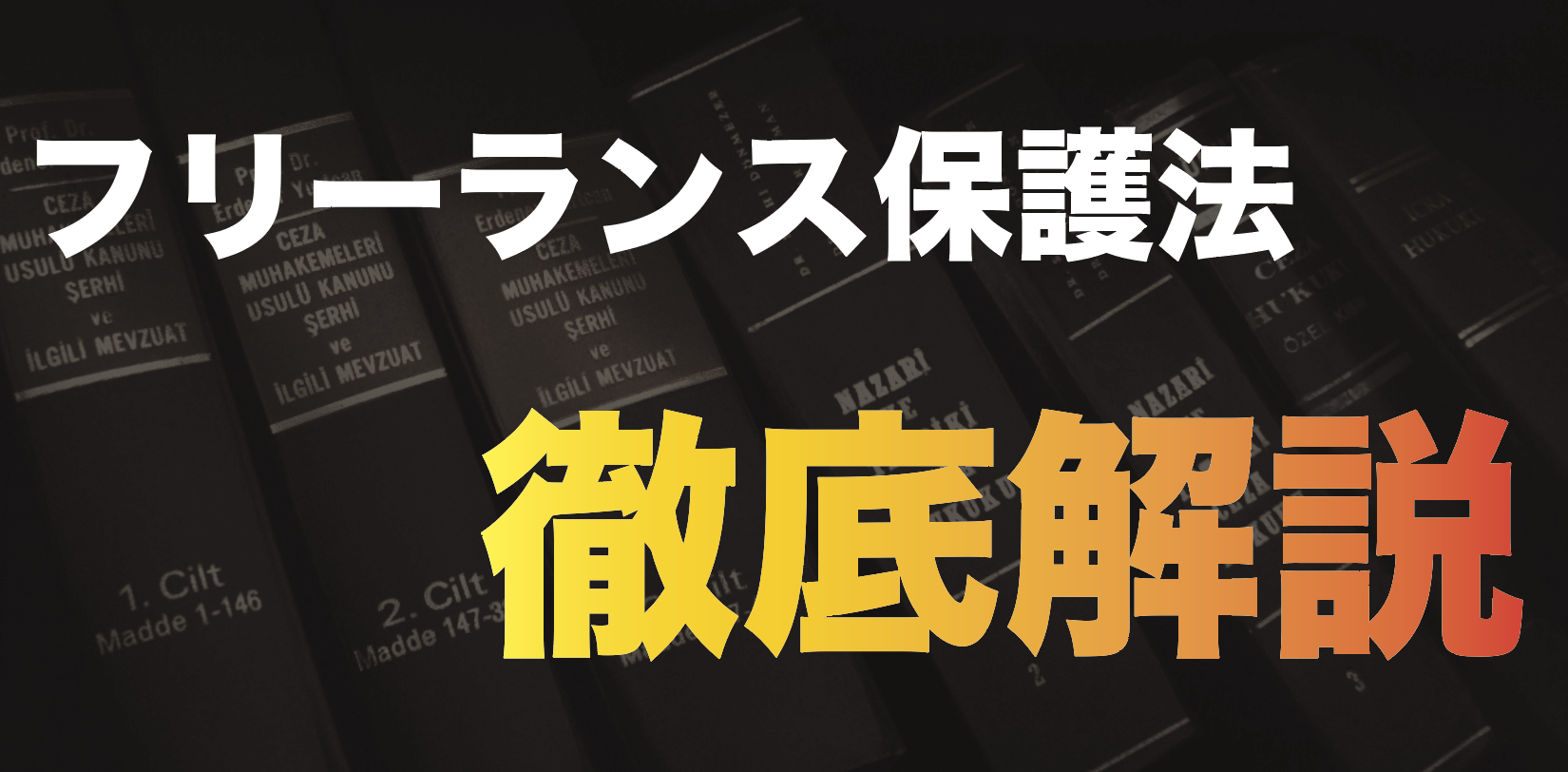「フリーランス保護法をよく知らない…」
「フリーランス保護法があれば安心して働けるのかな?」
ずっと憧れていたフリーランスとして独立したなら、トラブルが起きることなく安心して働き続けたいですよね。
しかし、「きちんと報酬が支払われなかった」や「クライアントに突然契約を解除された」という声も聞くため、フリーランスとして働くことに不安を抱く人も多いはず。
このような状況がある中、2023年4月28日にフリーランス保護法が制定されました。同法では、フリーランスが不利益を被らないよう様々な項目を発注者に義務付けています。
また、法律違反に対して罰則もあり、フリーランス保護を徹底しています。
そこで、今回は、フリーランス保護法はどのような法律か、基礎知識や知るべきポイントも交え解説していきます。違反した場合の罰則やフリーランス保護法の課題まで紹介するので、企業の方もぜひ参考にしてください。
- フリーランス保護法では、フリーランスが働きやすくなるよう、『業務内容や報酬の明示』『出産や育児、介護への配慮』『ハラスメント対応』『契約解除の予告義務』『具体的な取引の禁止行為』を発注者に義務付けています
- 同法に違反すると、個人だと50万円以下の罰金で、法人だと最大100万円支払う必要があります
フリーランス保護法の基礎知識

ここでは、まずフリーランス保護法の概要を5つにまとめて紹介します。
- 制定された背景
- 内容
- 対象者
- 施行日
- 下請法との違い
上記5つを具体例も交え、それぞれ解説していきます。
制定された背景
フリーランス保護法は、仕事上で立場が弱くなるフリーランスを守るために制定された法律です。極端にいえば、同法には『フリーランスと発注者を平等な関係にしよう』という考えがあります。
ランサーズの調査によれば、フリーランス人口は年々増加傾向にあります。2021年時点で、フリーランス人口は、過去最高となる1,577万人です。
フリーランスになれば、自由な働き方を実現できるなど幸せを感じられます。しかし、「クライアントとのトラブルで悩んでいる…」というフリーランスも少なくありません。
実際、内閣官房日本経済再生総合事務局によれば、フリーランスは以下のような悩みを抱えているそうです。
| トラブル内容 | 割合 |
|---|---|
| 報酬や業務内容を明確に明示されていない | 37.0% |
| 報酬の支払いが遅れる | 28.8% |
| 報酬の支払いがない・勝手な減額 | 26.3% |
| 業務内容や納品日を勝手に変更される | 24.4% |
| 業務内容で揉める | 23.5% |
| 報酬が相場より大幅に低いなど不利な条件で仕事をさせられる | 22.8% |
フリーランスが合っている上記のトラブルを見てみると、発注者と受注者の関係は、まるでドラえもんの『ジャイアンとのび太の関係』に似ているといえます。つまり、ジャイアン(発注者)は、好き勝手にのび太(受注者)を扱っているわけです。
フリーランスは、労働者を守ってくれる労働基準法が適用されません。そのため、報酬の遅延や無理な納期設定といったトラブルが起きても、泣き寝入りするしかない現状があります。
なかには、発注者から仕事をもらえないと生活できず、報酬やルールといった条件に納得していないまま取引してしまうフリーランスもいるほどです。
ただ、フリーランス保護法以前から、フリーランスが被る不利益を禁止する法律は存在します。たとえば、すでに存在するフリーランスを保護する法律には、次のようなものがあります。
なかでも、下請法は、特にフリーランスの働き方に関係する法律です。しかし、下請法が存在しても、フリーランスは、発注者から『報酬の未払い』などの不利益を被っています。
下請法が法律として機能していないのは、法律そのものに問題があるからです。
簡単に公正取引委員会の下請法の概要をまとめると、下請法は『稼いでいる会社だけ、下請法を守ってね』という法律です。要するに、小規模な法人は下請法を守らなくて良い、とも解釈できます。
具体的に、下請法の対象となる事業者は下記のとおりです。
- 発注する側:資本金1,000万円以上の法人
- 受注する側:個人または、資本金1,000万円以下の法人
下請法は、『お金の量』で法律の対象かどうか決まります。
ただ、内閣官房の調査によれば、フリーランスの約4割は資本金1,000万円以下の法人と取引しています。そのため、資本金の量だけで法律の対象者を決めている下請法は、フリーランスの保護に貢献していません。
このように、既存の法律の適用範囲が限定的であることを受け、フリーランス保護法が制定されたといえるでしょう。
内容
フリーランス保護法では、受注者が安心して働けるように発注者へ様々な内容を義務付けています。詳しくは後述しますが、厚生労働省によれば、同法のポイントは下記の6つです。
- 契約内容の明示:どういう案件を取り組むのか
- 報酬支払い期日の決定:報酬の支払いはいつまでか
- 取引の禁止事項の決定:理由なく成果物の納品を断らない
- 募集情報の的確な表示:案件の進め方はどうするのか
- ハラスメント対応の義務化:相談窓口を設置する
- 解除の予告義務:30日前に受注者へ契約解除を伝える
納期や報酬といった契約内容や取引条件は、フリーランスに曖昧な表現を使わず、『仕事内容は〇〇で、やって欲しい範囲は〇〇まで』などとはっきり伝えなければいけません。
また同法では、契約手続き時だけでなく、案件募集時においても取引条件の明示するよう義務付けています。
育児や介護への配慮も欠かせません。たとえば、発注者は、育児や介護を必要とするフリーランスのために、下記のような対応をしなければいけません。
- ハラスメント相談窓口の設置
- 介護や出産など離脱期間の人材不足に対応できる雇用を増やす
フリーランス保護法の内容を見ると、発注者に義務付ける項目が多く、「気づいたら違反していた…」となりかねません。違反してしまうと、下記の措置が取られます。
| 対象者 | 罰則 |
|---|---|
| 個人 | 50万円以下の罰金 |
| 法人 | 違反した人・法人の両方に50万円以下の罰金 |
法人が違反すると、違反行為をした会社内の人と法人自体にそれぞれ50万円以下の罰金が請求されます。つまり、最大で100万円の罰金を支払う可能性があります。
罰金を支払うだけでなく、周りから「法律違反している会社だよね」と見られるため、会社のブランドイメージが傷づくことも予測可能です。
フリーランス保護法では、これまでと違い、発注者は資本金の規模関係なく法律の対象となります。また、法律違反した際の罰則も強化されています。
そのため、契約内容が曖昧ではないか、受注者の不利益になっていないかを確認することが大切です。
発注者だけでなく、受注者も「この行為は法律違反じゃないかな?」と判断できるよう、何が良くて何をされたらダメなのか把握しておきましょう。
法律の対象

フリーランス保護法では、以下2つが法律の対象になると明記されています。
- 人:受注する側 / 発注する側
- 取引:業務委託 / 報酬
それぞれ具体例も交えて解説していきます。
対象となる人
前提として、フリーランス保護法は、仕事を受注する側を保護する法律です。そのため、仕事を依頼する発注者は守られません。むしろ、発注者は『法律を守らないと罰則を受ける』側になります。
先述したように、フリーランス保護法で対象となる人は以下の2つに分けられ、それぞれ特徴や対応が違います。
- 仕事を発注する側:法律を守る必要がある企業(人)
- 仕事を受注する側:法律に保護される人(企業)
まず、”仕事を発注する側”で法律の対象となる事業者を確認しましょう。
| 仕事を発注する側 | |
|---|---|
| 対象者 | 特徴 |
| 企業 | ・法人で、従業員や自分以外の役員が1人以上いる ・売上規模は関係なく適用される |
| 個人事業主 | ・従業員が1人以上いる ・売上規模は関係なく適用される |
簡単にいえば、下記のパターンに該当していれば、発注する側で法律の対象となります。
- パターン①:法人で、従業員や自分以外の役員(取締役・監査役など)が1人以上いる
- パターン②:個人事業主で、従業員が1人以上いる
法人でも、従業員や自分以外の役員がいなければ、法律を守るべき対象者でなくなります。つまり、1人社長は、フリーランス保護法で発注する側になりません。
逆に、個人事業主であっても、従業員を1人以上雇っていると法律が適用されます。
フリーランス保護法では、発注者は個人・法人ともに、昨期の部分は資本金額や売上など、事業規模関係なく、法律の対象になります。
発注する側は、フリーランス保護法に違反すると50万円以下の罰金です。法人の場合、違反した行為者と法人の両方に最大50万円ずつ支払いが請求されます。
続いて、”仕事を受注する側”で法律の対象となる事業者は下記のとおりです。
| 仕事を受注する側 | |
|---|---|
| 対象者 | 特徴 |
| 個人 | ・個人で、自分だけで仕事をしている ・売上規模は関係なく適用される |
| 企業 | ・”法人”であるが、従業員や自分以外の役員がいない1人社長 ・売上規模は関係なく適用される |
フリーランス保護法に守られる対象となるかどうかは、下記を踏まえ判断しましょう。
- 個人で、1人で依頼された仕事を進めている?
- YES:フリーランス保護法に守られる
- 法人で、従業員や自分以外の役員がいない1人社長?
- YES:フリーランス保護法に守られる
法人でも、1人で事業をしているとフリーランス保護法に守られます。また、フリーランス保護法では、売上が赤字でも年10億円以上稼いでいても、受注者は、事業の規模関係なく法律の対象です。
対象となる取引
法律の対象者が分かったところで、フリーランス保護法で適用される取引も理解しておきましょう。フリーランス保護法で対象となる依頼形態・事柄は下記のとおりです。
| 対象 | 特徴 |
|---|---|
| 業務委託 | ・企業や個人の業務を外部の事業者に依頼する ・勤務時間は決められない働き方 ・請け負った成果物を納品することが目的 |
| 報酬 | ・発注する側から受け取るお金 |
前提として、フリーランス保護法の対象となる取引は『業務委託』です。そのため、アルバイトや会社員など依頼する側と雇用関係がある業務形態には、法律は適用されません。
詳しくは後述しますが、フリーランス保護法の取引対象は、下請法よりも拡大されています。
具体的には、下請法にも含まれていたWeb・音声コンテンツ制作やコンサルティング業務だけでなく、物品の在庫管理やITのデータ分析業務まで法律の対象です。
施行日
フリーランス保護法は、まだ施行されていません。ただ、同法は、遅くても2024年秋頃までに施行されると考えられます。
そもそもフリーランス保護法は、2023年4月28年に成立しました。通常、法律は公布から1年6ヶ月以内に施行されます。
そのため、フリーランス保護法は、2024年11月頃までに施行されると予測できます。
法律は、違反しても「知らなかった…」じゃ済まされません。そのため、いつフリーランス保護法が施行されるのか、ニュースで確認してくださいね。
下請法との違い
フリーランス保護法と下請法は、適用される範囲や対象者、罰則などがそれぞれ異なります。具体的な違いは、下記のとおりです。
| 項目 | フリーランス保護法 | 下請法 |
|---|---|---|
| 概要 | 全てのフリーランスの立場を改善する | 一定以上の資本金がある発注事業者を取り締る |
| 対象者 | ・発注する側:自分以外に従業員や役員(取締役・監査役など)が1人以上いる全ての法人 ・受注する側:自分1人だけで事業している全ての個人(法人) | ・発注する側:資本金が1,000万円以上の法人 ・受注する側:個人または、資本金が1,000万円以下の法人 |
| 対象取引 | 物品の製造 / 情報成果物作成 / 役務の提供 | 製造委託 / 修理委託 / 情報成果物作成委託 / 役務提供委託 |
| 罰則 | ・50万円以下の罰金 ・法人の場合は、行為者と法人両方に50万円以下の罰則が適用 | ・50万円以下の罰金 |
フリーランス保護法と下請法は、両方とも受注する側を守るための法律です。そのため、内容に大きな違いはありません。
ただ、対象となる人・取引は、フリーランス保護法と下請法で異なります。
下請法の場合、対象となる人は、『資本金が1,000万円以上の法人』『個人または資本金が1,000万円以下の法人』です。
一方、フリーランス保護法は、売上や資本金額など事業規模に関わらず発注者・受注者は法律の対象です。
フリーランス保護法では、対象となる取引も下請法より拡大されています。たとえば、フリーランス保護法の対象取引で、下記のような業務は下請法にはありません。
- データ分析する業務
- ITデータベースを管理する業務
- 在庫の数量や品質の管理をする業務
- 倉庫へ物品の入庫と出庫を記録して管理する業務
上記は一例ですが、フリーランス保護法の取引対象には、下請法で適用外であるITの業務全般と物品の倉庫管理まで含まれています。
このように、フリーランス保護法と下請法は別の法律であるものの、補完的な関係であるといえるでしょう。
フリーランス保護法でおさえたい6つのポイント

フリーランス保護法の概要について理解が深まったところで、ここからはフリーランス保護法でおさえたいポイントを6つ紹介します。
- 契約内容の明示
- 報酬支払い期日の決定
- 取引の禁止事項の決定
- 募集情報の的確な表示
- ハラスメント対応の義務化
- 解除の予告義務
それぞれ詳しく解説していくので、「どう働き方が変わるのかな?」と考えながら読み進めてくださいね。
1.契約内容の明示

フリーランス保護法では、契約内容の明示を発注者に義務付けています。たとえば、発注者は、下記のような項目をフリーランスに明示しなければいけません。
- どのような業務内容か
- 報酬はどう設定するのか
- 支払い期日はどうするのか
- 契約解除したい場合はどうするのか
契約内容の明示で重要なのは、報酬や納期といった業務上の取り決めを、紙またはデータ(PDFなど)としてフリーランスに公開することです。
今まで、フリーランスは口約束やチャットメッセージで業務のルールを合意させられる場面もありました。そのため、仕事をやってみると、業務内容や納期など取引条件が「これは初耳だった…」といったケースもあります。
下請法では支払日や納期などの契約内容が明確に定められていますが、資本金が1,000万円以下の発注者には適用されません。
ただ、フリーランス保護法では、発注者は、資本金など事業規模に関わらず契約内容の明示が義務付けられます。そのため、フリーランスは納期や報酬など業務上のルールで「言った言っていない」と揉めることはなくなるでしょう。
なお、どういった契約内容を明示するかといった詳細のルールは公正取引委員会規則で決められる予定ですので、常に動向は追っておきましょう。
2.報酬の支払期日の決定

フリーランス保護法では、報酬の支払い期日も明確に定められています。
内閣官房のフリーランスの実態調査で示したとおり、期日までに報酬が支払われなかったフリーランスは約30%います。
フリーランス保護法では、発注者は、フリーランスから成果物が納品されて60日以内に報酬を支払うよう義務付けられています。支払い期日が60日を過ぎる場合は、できるだけ短い日数での支払いが必須です。
ただ、他の事業者から請け負った案件を、発注者が受注者に再委託する場合は、報酬の支払い期日は30日以内です。
受注する側にとって報酬は、命と同じくらい大切です。受注者の生活に影響することなため、発注者はきちんとルールを守ってくださいね。
3.取引の禁止事項の決定

フリーランス保護法では、以下の6つを禁止事項と定めています。
- 正当な理由なくフリーランスが納品した成果物の受け取りを拒否する
- 正当な理由なく報酬を減らす
- 正当な理由なく成果物の納品後にそれを引き取らせること
- 似たような成果物に対して通常の報酬より大幅に報酬額を減らすこと
- 正当な理由なく商品を購入させたり発注者のサービスを利用させる
- 利益の提供や報酬内容の変更、やり直しでフリーランスの利益を害する
下請法でも、上記で挙げたような自身の強い立場の悪用を規制しています。しかし、下請法には次のような課題があります。
- 資本金額や売上など、事業規模によっては法律の適用外
- 内容が具体的でない
フリーランス保護法では、資本金や売上など事業規模に関わらず、発注者が法律の対象となります。
また、個人が法律違反したら、50万円以下の罰則です。法人の場合は、違反した人・法人両方にそれぞれ50万円以下の罰金が課せられます。
このように、フリーランス保護法は、下請法とは違い、罰則が強化されています。そのため、フリーランスはこれまでより、不当な契約解除など不利益を被らないでしょう。
4.募集情報の的確な表示

フリーランス保護法では、募集時についてもルールが決められています。発注者は、案件の応募者を募る際、下記のことが義務付けられます。
- 正確で最新の情報を載せる
- 誤解を生むような表現は記載しない
- 報酬や納期など条件を明確に表示する
- 募集時点と条件が変わる場合はフリーランスに説明する
これまで案件の募集に関する明確な取り決めがなかったため、フリーランスが実際に仕事を進めると、「あれ?伝えられた内容と違う…」「報酬額が少し減っている…」といった認識のズレを経験しています。
しかし、フリーランス保護法では、具体的に『報酬は〇〇円』と募集時のルールが決められています。そのため、クライアントと業務上のルールで認識のズレは起きずらいでしょう。
5.ハラスメント対応の義務化

フリーランス保護法では、ハラスメント対応や育児・介護への配慮といった、個人の仕事環境に関するルールも決められています。
フリーランス保護法14条によれば、発注者は、フリーランへ案件を継続的に発注する場合、下記に関する配慮が義務付けられます。
- 妊娠
- 出産
- 育児
- 介護
発注者は、ハラスメント対応として相談窓口を設けるのがおすすめです。妊娠・介護への配慮としては、下記のような対応ができると考えられます。
- 保育所や搾乳室といった施設面での支援
- 子どもの突発的な体調不良などに対応できる人材体制の準備
- 援助金など支援制度を作る
フリーランス白書2022では、女性の50.3%がフリーランスとして働いています。
女性・男性にとって、妊娠や出産、育児は、仕事と同じくらい向き合いが必要となるものです。しかし、フリーランスが育児や介護などで長期間仕事から離脱する場合、発注者は契約解除するなど自分の都合を優先しています。
そのため、なかには契約解除されるのが怖く、「長期離脱すること言いづらいな…」と思い悩むフリーランスもいるほどです。
フリーランス保護法では、育児や介護への配慮を発注者に義務付けているため、きっと「安心して育児や介護に取り組める!」となりますよ。
6.解除の予告義務

フリーランスへ継続的に仕事を依頼する際、発注者は30日前までに契約解除を伝える義務があります。フリーランスが契約の解除理由を請求できるようにしたのもポイントのひとつ。
フリーランスは会社員ではないため、労働基準法が適用されません。そのため、『急な契約解除』や『不当な契約解除』といった不利益を被りやすい傾向にあります。
フリーランス保護法では、30日前に契約解除を予告するよう義務付けているため、フリーランスは焦って次の仕事先を探す心配はありません。
不当な契約解除を受けた場合、フリーランスは解除理由の開示を請求して適切かどうか主張しましょう。
国民の声から紐解くフリーランス保護法の良い・悪い評価

上記では、フリーランス保護法のポイントを解説しましたが、なかには「フリーランス保護法って客観的に見たらどうなの?」や「フリーランスは法律内容に満足してるの?」と疑問を抱く人もいるはず。
受注者を保護する法律であるからこそ、フリーランス自身が満足できるかどうかは大切ですよね。そこで、ここではフリーランス保護法について国民の良い評価・悪い評価をそれぞれ紹介します。
実際の口コミを踏まえて解説するので、ぜひ参考にしてくださいね。
良い評価
まず、フリーランス保護法の良い評価を紹介します。良い評価は、以下の2つです。
- 会社だと当たり前なことがやっと実現だ
- フリーランス保護法を早く施行して
それぞれ詳しく解説していきます。
会社だと当たり前なことがやっと実現だ
フリーランス保護法👀募集内容と仕事内容が全く違うこと、口約束で業務をお願いすること、未払い…などなど、企業より立場が弱くなりがちなフリーランスを守る法律!つまり契約書ベース、作業依頼書ベースでお仕事始めよう!ってことだね😊会社だと当たり前のことがなぜ今までほったらかしだったの?!
引用元:Twitter(@まいちゃん)
同じ労働をしていても、フリーランスは会社員とは待遇が異なります。具体的に、会社員とは異なり、フリーランスは次のような恩恵が受けられません。
- 有給
- 老後の資金が増える厚生年金への加入
- 過労死などから身を守れる労働基準法の適用
ただ、フリーランス保護法は、受注する側の働き方全体を変えようという法律です。
会社員と完全に平等な立場にならないものの、長時間労働や報酬の未払いなど不利益を被らなくなるでしょう。
フリーランス保護法を早く施行して
零細フリーランスのために・・・インボイスよりフリーランス保護法を先にお願いしたい…と思う今日この頃。
引用元:Twitter(@ぱとぴー)
現在、フリーランス保護法は施行されていません。しかし、フリーランス保護法の施行を求める人は多い傾向にあります。
フリーランスの保護が目的でもある下請法や独占禁止法は、法律の適用範囲が限定的など課題が存在します。そのため、フリーランスの立場を改善することに大きく貢献はしていません。
フリーランス保護法では、介護や育児への配慮やハラスメント対応といった個人に関するルールが明記されています。つまり、『受注する側の保護』を第一に考えています。
そのため、フリーランスの働き方にプラスの影響を与えると考える人が多いのでしょう。
悪い評価
続いて、フリーランス保護法の悪い評価を2つ紹介します。
- フリーランスに不利益がないようにしてほしい
- 募集時に事業者の情報をもっと開示すべき
それぞれ下記で詳しく解説していきます。
フリーランスに不利益がないようにしてほしい
フリーランスに対する発注控えや取引停止につながることのないよう、内容について慎重に検討すべき
引用元:内閣官房パブリックコメント
フリーランス保護法は、契約解除の予告義務やハラスメント対応など、数多くの項目を発注者に義務付けています。そのため、なかには「ちょっと厳しいから発注やめとこう…」といった発注者がいる可能性もあります。
フリーランスの立場を改善するために、厳格にルール化するのは重要です。しかし、厳しくした結果フリーランスの仕事が減ることは避けたいですよね。
ただ、フリーランス協会によれば、ハラスメント対応や育児への配慮など負担が増えることで、事業者が発注控えしてしまうのは良くないと発表しています。そのため、国に法律内容の追加を求める働きかけをするでしょう。
募集時に事業者の情報をもっと開示すべき
募集時に表示する内容として、事業者の住所、代表者氏名、連絡先を定めるべき
引用元:内閣官房パブリックコメント
フリーランス保護法では、案件への募集を募る際、報酬や納期など業務内容を正確に明記するべきと発注者へ義務付けています。
しかし、発注者の住所や事業の代表者、連絡先までは明示する必要がないため、情報開示の範囲に不満を抱く人もいるようです。
発注する側の住所や連絡先など個人情報が分かれば、何かトラブルが起きても対処が楽ですよね。しかし、個人情報保護といった側面から、発注者のあらゆる情報を開示するのは難しい現状があります。
フリーランス保護法の違反となる行為とその罰則

フリーランス保護法は、発注控えなど課題があるものの、フリーランスにとって有効な法律です。とはいえ、違反した際の罰則が重くないと法律の拘束性が弱まるのも事実です。
フリーランス保護法では、違反した場合の対応は次のように明記されています。
公正取引委員会、中小企業庁長官又は厚生労働大臣は、特定業務委託事業者等に対し、違反行為について助言、指導、報告徴収・立入検査、勧告、公表、命令をすることができるものとする。※ 命令違反及び検査拒否等に対し、50万円以下の罰金に処する。法人両罰規定あり。
引用元:フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性
上記でわかるように、法律違反しても、即座に罰金を課されるわけではありません。
まず、法律違反した発注者に、国が『〇〇をしなさい』と対処法を指示します。この指示や命令に従わないと、50万円以下の罰金です。
命令に従わないと課される罰金は、個人か法人かどうかで金額が異なります。
なお、フリーランス保護法の違反と判断されうる行為は、たとえば以下が考えられます。
- 発注者がいきなり契約解除する
- 案件の募集内容で報酬や納期を記載しない
- 発注者がフリーランスの成果物に対して1年以上報酬を支払わない
- 介護や育児などと仕事を両立したいフリーランスに対して悪態を取る
- 契約の際、報酬や納期など条件を濁す
- フリーランスにとって不利益となるような行為をする
発注者は、報酬や納期など業務上の条件を明確に伝えることが大切です。育児や介護への配慮も必要となるため、育児給付金制度や介護援助金制度の導入といった対応を検討しなければいけません。
フリーランス保護法では、細かく禁止事項やルールが記載されているためよく確認してくださいね。
フリーランス保護法の3つの課題

これまでフリーランス保護法のポイントや罰則を解説してきて、「これでクライアントとトラブルがなくなりそう!」と前向きになった人もいるでしょう。
しかし、フリーランス保護法は、フリーランスにとってまだ万全な法律とはいえません。ここでは、フリーランス保護法の課題を3つ紹介します。
- 課題①:事業者の負担増加で業務委託に影響を与えることもある
- 課題②:フリーランス自身が違反された旨を申告する必要がある
- 課題③:口約束での決め事に適用されるのかは不明
それぞれ下記で詳しく解説していきますね。
課題①:事業者の負担増加で業務委託に影響を与えることもある
発注者がフリーランスへの案件依頼を控える可能性があります。
フリーランス保護法によって、ハラスメント対応など体制準備で発注者の負担が増えます。そのため、発注者は事業をフリーランスに依頼するのではなく、社内で実施しようとする可能性もあります。
フリーランスへの発注控えが起きてしまえば、フリーランスにとって生活の糧が減ってしまうため、大きなダメージです。
ただ、フリーランス協会などは、発注者の負担が増えてフリーランスが案件獲得できなくなるのは望ましくないと発表しています。そのため、法律内容の追加を政府に働きかけるでしょう。
案件の獲得は、生活していくうえで非常に重要な部分ですので、どうなるのか常に目を配ってくださいね。
課題②:フリーランス自身が違反された旨を申告する必要がある
フリーランスは、法律違反された場合、自分自身でその旨を申告しないといけません。なぜなら、中小企業庁のような法律違反を取り締まる機関が未だ存在しないからです。
法律違反されたことを自己申告となれば、なかには「契約解除されそうだから、報告するのはやめておこう」というフリーランスも出てきてしまいます。
フリーランス保護法が施行されても、違反を積極的に申告できる環境がないと法律がうまく働くとはいえないでしょう。
課題③:口約束での決め事に適用されるのかは不明
フリーランス保護法が口約束に適用されるかどうか、まだ明確に決められていません。前提として、フリーランス保護法で対象となるのは『業務委託』です。
口約束は、納期やルールといった契約内容を紙やデータとして明示しません。そのため、業務委託に該当しないのではないか、というのが論争の的です。
フリーランス協会によれば、クライアントとトラブルを起こしたフリーランスの約45%は『口約束』であると発表しています。金銭のやり取りが発生する仕事であっても、「まぁ大丈夫でしょ」というフリーランスは多い傾向にあります。
そのため、フリーランス保護法が口約束に適用されるのかは非常に重要なポイントです。
フリーランスは、報酬や納期など取引条件で発注者と揉めないように、必ず契約の締結をするよう心がけましょう。
フリーランス保護法の施行後に起こる企業・フリーランス側への影響

フリーランス保護法はまだ施行されていないとはいえ、発注者もフリーランスも「法律によって具体的にどのような影響受けるの?」と自身の待遇が気になるのは当然です。
ここでは、フリーランス保護法の施行後に起こる影響を企業・フリーランス別で紹介します。それぞれ具体例も交え、解説していくのでぜひ参考にしてください。
企業側
発注者は、フリーランス保護法の施行後、契約手続きや仕事の進め方など様々なことで変化があると予測されます。
たとえば、企業側は、次のようなことを把握しておくのが賢明です。
- 契約手続きやフリーランスの募集に、手間・時間がかかる
- 契約を解除する際、納期の遅延など正当性のある理由がないといけない
- ハラスメント対応や育児・介護への配慮に、手間・時間がかかる
- 上記の対応の効果を検証し、場合によっては改善しないといけない
発注者は、ハラスメント対応や育児・介護への配慮といった体制準備に時間を割かなければいけません。
また、発注事業者の規模に関わらず、違反した場合には罰則があるため、契約書や募集文の内容をかなりの労力で確認することが必要です。
ただ、フリーランス保護法が施行されれば、発注者にとって、下記のような良い影響もあります。
- 納期や報酬など取引条件について、受注者の言い訳がなくなる
フリーランスの中には、契約書できちんと伝えていても「これは違う!」と何かと言い訳をしてくる悪質な受託者も存在します。
しかし、フリーランス保護法により、募集内容や契約内容には納期や報酬などの正確な情報が記載されます。そのため、フリーランスとのトラブル対処で時間がかかることはなくなるでしょう。
フリーランス側
続いて、同法は次のような影響をフリーランスに与えます。
- 無理な納期設定や報酬の未払いなど、不利益を被る可能性が低くなる
- 突如、契約の解除をされることがなくなる
- 契約を解除されても、解除理由の開示を請求できる
- 育児や介護と仕事を両立できるようになる
フリーランス保護法が施行されると、契約内容や募集内容などの条件を明確に提示されるため、報酬の未払いや急に業務内容が変わるなどトラブルに合うことは少なくなります。
そのため、今までより働きやすくなると予測されます。
ただ、発注者から、納期や業務内容を明確に提示されるため、「これは聞いてなかった」など契約に関する言い逃れはできなくなるでしょう。
フリーランス保護法の施行までに企業・フリーランスがやるべきこと

上記で解説したとおり、フリーランス保護法によって発注者・受注者は、働き方が変わります。そのため、フリーランス保護法が施行されるまでに何をやるべきか、を知っておくのが賢明です。
法律が施行されてから様々な対応を考えると負担が多くなり、きちんとした体制が準備できません。
そこで、ここではフリーランス保護法の施行までに企業・フリーランスがやるべきことを、解説していきます。それぞれ詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
企業の場合
まず、フリーランス保護法の施行までに発注者がするべきことは下記の3つです。
- 受注側に取引条件を開示できる体制の準備
- 仕事と育児・介護の両立を考えている受注側への対応
- ハラスメントへの対応
上記3つを具体例も交え、解説していきます。
受注側に取引条件を開示できる体制の準備
発注者は、取引条件を受け取り側に開示できる体制を整える必要があります。
先述したとおり、フリーランス保護法では、募集内容や契約内容を書面やデータ(PDFなど)で漏れなく記載することが発注者に求められてます。
そのため、契約手続きに今までより時間・手間がかかり、コピー代や人件費といったコストや精神的なストレスが増えることも考えられます。
発注者は、なるべく自身の負担が軽減するような、取引条件の開示体制を整えるのが大切です。なお、取引条件をどう開示するのかは、下記2つのポイントを踏まえて考えましょう。
- フリーランスに不利益がないか
- 契約内容に曖昧性がないか
どのような契約内容を契約書に記載するかといった詳細なルールは、今後決められる予定です。ですので、政府のフリーランス保護法に関する動向をよく確認しておきましょう。
仕事と育児・介護の両立を考えている受注側への対応
フリーランス保護法は、継続的に発注する場合、育児・介護への配慮を発注者に義務付けています。
受注する側が育児・介護で長期間離脱する場合に備え、発注者は下記についてどうするのかを考えることが重要です。
- フリーランスは長期間離脱することを言いづらい
- 仕事がスケジュール通り進めなくなる
- 人材不足になる
出産や育児、介護に関する具体的な対応策としては、以下が考えられます。
- 社内に育児施設を作る
- スムーズに育児ができるよう講座を開催する
- 離脱期間に備え、人材を増やす
- 綿密にコミュニケーションを取り、新しい対応を考える
研修や講座を開催してストレスなく、育児や介護が乗り越えられる体制を準備するのは良いでしょう。
実際に育児施設を作って仕事と両立させてあげられるようにするのも、フリーランスには嬉しいはずです。
ハラスメントへの対応
発注者は、ハラスメント対応として下記のような策をやってみるのが良いでしょう。
- ハラスメント対策の研修を開催する
- 周りが気付きやすいように、一緒に仕事をしている人にアンケートを実施する
- 代表自身が強くハラスメント撲滅を掲げる
なかでも、代表自身が「ハラスメントは許せない!」と強くメッセージを発信するのがおすすめです。企業や事業のトップがハラスメントを撲滅する意識を持たないと、そもそもの本質は変えられません。
受注者とのミーティング内でハラスメント撲滅を発信したり、実際にビデオメッセージを送るなどしましょう。
フリーランス側の場合
フリーランス保護法は、発注者を対象とするため、フリーランス側が何かしらの体制を整えることはありません。
ただ、法律が施行されれば、フリーランス自身の働き方は変わります。そのため、下記2つを事前にやっておくのが良いでしょう。
- 業務上で変わることがあるか相談する
- 契約履行の責任感をよりいっそう強める
それぞれ下記で、わかりやすく解説していきます。
業務上で変わることがあるか相談する
フリーランスは、業務上で変わることがあるか、発注者に相談しましょう。これまで解説してきたとおり、フリーランス保護法は、育児・介護への配慮や取引の禁止行為など様々なことを発注者に義務付けています。
そのため、納期や案件の進め方など変更される可能性があります。具体的に、フリーランスは、下記の項目を発注者に聞いておくのが良いでしょう。
- これまで通り継続して案件を発注してくれるか
- 報酬や業務上のルールに変更はないか
- 出産や育児、介護への具体的な対応策はあるのか
- ハラスメント対応の具体策は何か
法律の施行後に業務上の変化がわかれば、「あれ?どうすれば良いの?」と戸惑いかねません。ですので、上記以外にもフリーランス自身で不安な点があれば、遠慮せず発注者に相談しましょう。
契約履行の責任感をよりいっそう強める
契約履行の責任感をいっそう強める必要があります。
先述したとおり、納期や報酬といった契約内容や取引条件については、今後明確に決められます。そのため、フリーランスは「これは聞いてないからやっていないだけ」と言い訳ができなくなるでしょう。
発注者は、フリーランス保護法への様々な対応で時間を割きます。そのため、フリーランス側も発注者の苦労を無駄にしないようにするのが大切です。
フリーランス保護法と似ていて知っておくべき2つのガイドライン・相談窓口

フリーランスとして働くうえで知っておくべきなのは、フリーランス保護法だけでありません。
ここからは、フリーランス保護法と似ている知っておくべきガイドライン・相談窓口を2つ紹介します。
- フリーランスガイドライン
- フリーランストラブル110番
それぞれ具体例も交え、分かりやすく解説していきますね。
フリーランスガイドライン
フリーランスガイドラインは、フリーランスの立場を改善する目的で策定された指針です。
フリーランス保護法以前にも、『下請法』や『独占禁止法』といった受注者を守る法律が存在します。しかし、受注者を第一に考える法律ではないため、「受注者はどう守られるの?」と疑問の残る部分が多くありました。
こういった状況を受けて、フリーランスガイドラインでは、受注者がどう保護されるのかや、どういう発注者の行為が違反であるのかを明確にしています。具体的には、以下の4つです。
- フリーランスの定義:どういう受注者が守られるのか
- 独占禁止法と受注者の関係性:どのような行為が法律違反になるのか
- 下請法と受注者の関係性:どういう行為を発注者はしていけないのか
- 労働関係法令と受注者の関係性:受注者を法律上の労働者として判断できないか
フリーランスガイドラインの内容は、以下の参考にしてください。
| 決定事項 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| フリーランスの定義 | ・実店舗がなく、雇用している人がいない個人(法人) ・自身の経験や知識を活用して報酬を得る個人(法人) | ・1人で活動する個人事業者 ・1人社長 |
| 独占禁止法との関係性 | ・事業者とフリーランスの間に適用されると明記 | ・地位を利用してフリーランスを害してはいけない ・取引条件を明確に提示しないことはNG |
| 下請法との関係性 | ・資本金1,000万円以上の事業者とフリーランスに適用されると明記 | ・報酬の遅延はいけない ・一方的な減額はいけない |
| 労働関係法令との関係性 | ・フリーランスが法律上『労働者』じゃなくても、働き方の実態で判断するようにと明記 | ・長く仕事を依頼している受注者は、法律上『労働者』と判断しても良い |
上記のように、フリーランスガイドラインでは、どのような発注者の行為がフリーランスに対して違反となるのかなど詳しく定義されています。
フリーランスガイドラインが策定され、『フリーランスの立場を改善していこう!』という活動が活発になったともいえるでしょう。
フリーランス・トラブル110番
フリーランス・トラブル110番は、フリーランスにとって相談機関となる窓口です。上記のフリーランスガイドラインと同年に、弁護士会が内閣官房や厚生労働省と連携して設置しました。
発注者がフリーランス保護法に違反した場合、フリーランスはその旨を自己申告しなければいけません。そのため、なかには「仕事が貰えなくなる可能性もあるからやめとこう」と思い留まる人がいることも予測できます。
フリーランス・トラブル110番は、匿名で相談も可能です。そのため、契約の解除を恐れる受注者にとって、気軽な相談ができます。
料金は無料となっているので、自分で対処できないと思ったら『フリーランス・トラブル110番』をぜひ活用してください。
フリーランス保護法にまつわるFQA

最後に、フリーランス保護法にまつわるよくある質問を3つ紹介します。
- フリーランス保護法の今後のスケジュールは?
- フリーランス保護法に追加されそうな項目はある?
- もしフリーランス保護法に違反されたらどうすれば良い?
それぞれ下記で解説していきます。
フリーランス保護法の今後のスケジュールは?
フリーランス保護法は、遅くとも2024年11月頃までには施行されるでしょう。
現時点のフリーランス保護法は、契約明示の詳細ルールなど具体化されていない項目が多い傾向にあります。
そのため、2024年11月前より、下記の項目を段階的に決めていくと予測されます。
- 法律を具体化する政令
- 公正取引委員会規則
- 厚生労働省令
- 各種方針
- ガイドライン
フリーランス保護法によって、発注者は、契約手続きや介護・育児への配慮など対応することが増えます。そのため、上記で挙げた取り決めは、施行に先立ち、2023年中または2024年2月までに発表されるでしょう。
2023年または2024年2月頃に発表されるであろう同法の各種方針やガイドラインを、よく確認してくださいね。
フリーランス保護法に追加されそうな項目はある?
フリーランス保護法に追加されそうな項目は、下記の3つが考えられます。
- フリーランス側からの契約解消できるようなルール:事故や妊娠など場合によっては、違約金なしで契約解除できる
- フリーランスの長時間労働に関する規制:〇〇時間しか案件に取り組めない
- フリーランスの優遇に関するルール:雇用保険への加入
フリーランス保護法で、フリーランスの働き方はプラスになると予測される一方、対処しないといけない課題は多く残っています。
たとえば、フリーランス側から契約の解消ができないことです。フリーランスは、体調不良や不慮の事故などで業務をスケジュール通りに進められなくなっても、契約解除に違約金があったりして取引を終了できない現状があります。
長時間労働もフリーランス側の課題のひとつ。加えて、会社員とは違い、フリーランスは雇用保険や健康保険、厚生年金に加入することが難しい傾向にあります。
このように、まだまだフリーランスが働きやすい環境整備には課題があります。そのため、上記のような項目がフリーランス保護法に追加される可能性はあるでしょう。
もしフリーランス保護法に違反されたらどうすれば良い?
フリーランスは、発注者に法律違反された場合、自己申告する必要があります。そのため、無料の相談窓口『フリーランス・トラブル110番』にお問い合わせしてください。
フリーランス・トラブル110番は、弁護士会と政府が連携して設置された窓口であるため、安心してトラブル対処の相談ができますよ。
まとめ

今回は、フリーランス保護法はどのような法律か、具体例も交えて解説しました。
フリーランス保護法は、フリーランスが発注者から数多くの不利益を被っている背景があり制定された法律です。同法でおさえたいポイントは、下記の6つになります。
- 契約内容の明示
- 報酬支払い期日の決定
- 取引の禁止事項の決定
- 募集情報の的確な表示
- ハラスメント対応の義務化
- 解除の予告義務
これまでも、下請法や独占禁止法でフリーランスは守られてきましたが、発注者の規模によって適用されなかったり、個人の仕事環境に関する規制を設けることが困難でした。
フリーランス保護法では、ハラスメント対応や介護や出産への配慮を発注者に義務付けています。そのため、下請法や独占禁止法よりも法律として機能するはず。
ただ、同法の施行日は、未定となっています。2024年11月ごろまでには施行されると予測できるため、常に動向に目を配ってくださいね。